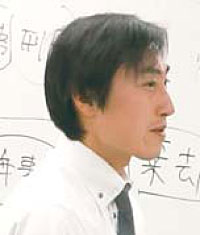3.模擬民事裁判「いじめPTSD事件」-「役割実践法」からいじめ問題の出口を捜す-
今回、法教育班が提案する模擬民事裁判「いじめPTSD事件」(3月3日(日)実施)は、単なる模擬裁判ではない。 実は、前段があり、いじめ事件が発生した段階での学校における学年会議や職員会議を再現している点にある(2月21日(木)実施)。 いじめ問題が起こると、テレビ報道では、校長や教育長の謝罪シーンばかりを映すが、学校の会議の様子は全く見えてこない。 この企画では、その見えない部分を教職をめざす学生に模擬体験させ、問題解決に向けた会議の手順や適切な対応を考える体験をさせている。 教職の専門的知識だけではなく、技能や行為が一体化して初めて実践力となる。事件が発生して学ぶのでは遅い。 問題は教師の経験の蓄積を待ってはくれないのである。私たちは、これから教師になる学生に適切な対応を思考させる模擬体験を実施した。 これらに続き、当模擬民事裁判が実施される。
模擬「拡大学年会議・緊急職員会議」-桃ヶ丘中学校で「いじめ事件」-発生
2011年9月10日朝、A県A市にある桃ヶ丘中学校で、前日放課後「いじめ事件」が発生していたとの通報が入った。 同校3年2組の佐伯原由香が、同級生4人から暴行を受け、額に2週間の傷を負ったというのだ。 彼女の父親からの一報だった。体育館裏で4人に脅され、押し倒されて怪我をしたとのことである。 電話を受けた教頭は、校長が不在であったが、すぐに、第3学年の教員と教務主任、生徒指導部の教員を召集して、第1回拡大学年会議を開催し対応策を出した。 会議後には、担任と学年主任が佐伯原宅へ訪問を行うと共に、他の教員も欠席している4人の生徒の家庭に連絡等を素早く行った。
佐伯原宅では、怪我をし憔悴しているという由香への面会はできなかったものの、両親からは事件の状況を確認することができた。 しかし、この時、両親から、担任の井ノ頭が由香から「いじめ」の相談を何度も受けていたのに、十分な対応をしていなかったと批判された。 井ノ頭はこの指摘を認め謝罪した。一緒に訪問していた学年主任の井上は驚きを隠せなかった。
11日朝の段階までに、4名の生徒の面談も終了し、大筋で佐伯原の両親の話と一致していることが確認されたが、由香が押し倒されたのか、バランスを崩して自ら転倒したのかは曖昧だった。
この日、事情聴取等の結果を受けて、第2回拡大学年会議が開催された…
シナリオは、ざっと、以上のような話から始まる。将来教師をめざす学生は、桃ヶ丘中の26名の教員役を担当し、この「いじめ事件」について対応策を議論して、解決策を探るのである。
こうした教師の役割体験(模擬体験)を通して、問題を認識し適切に解決する知識と技能を身に付けるのである。
この体験は、2月21日(木)に実践されたが、その様子については、秋田魁新報(23日(土)、27面)に掲載されたので 一部紹介しておきたい。
教員志望の学生に、学校現場でのいじめについて考えてもらう研究会が21日、秋田市の秋田大手形キャンパスで開かれた。 同大教育文化学部の学生約30入が参加、職員会議でいじめ問題への対応を協議する教員を模擬体験した。

学生たちは、勤務する中学校で女子生徒が同級生から暴力を受けたとの設定で、対応を議論。 「事実確認が当事者同士でしか行われていない。他の生徒にも聞くべきだ」「いじめ問題は一人では対応できない。 他の教員にも早めに相談するべきだ」など、それぞれの考えをぶつけ合った。
4年の田島駿己さん(22)は「臆せずに自分の意見を出すことが、いじめ問題の早期解決につながると感じた」と話した。
研究会を企画した教育文化学部の井門正美教授(教育学)は「いじめ問題が解決するか、こじれるかは学校の対応にかかっている。
模擬体験を通し、教員としていじめにどう対処するべきかを今から考えてほしい」と述べた。 (以下略)
*三戸忠洋記者の記事 *写真は記事とは別